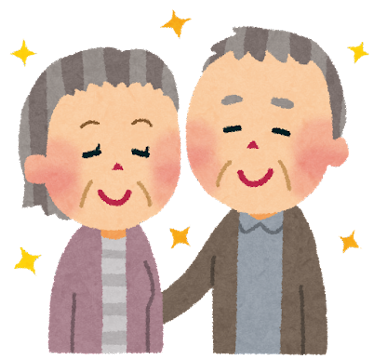これからも、つの町でまるっと
1,135view
3年ほど、ほぼ毎日な感じでお届けしましたけんこう日記。この3月末で、いったん区切りとなります。
コロナ禍で地域での活動が制限されるなか始まった「つのまる」ですが、ポストコロナの活動が増えていく中、一定の役割は終えたかと考えています。
今後は不定期になりますが、都農町での健康に関する取り組みなど報告できたらと思います。
つのまるケアミーティングという、町内の保健医療福祉の専門職の定期的な会合も始まりました。
地域住民向けのリアルでのイベント(健康講話など)もこれから増えていくと思います。
もし体調不良など健康問題があれば、気軽に病院へご相談ください。
これからも都農町民の健康や幸せの種が増えていきますように。
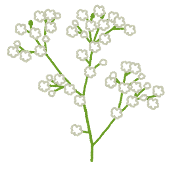
けんこう日記– archive –
-

久しぶりの日常
久しぶりのつのまるナース。 コロナ禍から体も気持ちも少し解放されたここ最近。 コロナ禍のおかげで 何年振りだろうというくらい期間があいてしまったけど。 都農にあ... -

未来の社会や地域を見据える
高齢化率の上昇や人口減地域といったところでは、都農町は日本の先端地域の一つです。人口が現在の1万人弱から、2040年には6千人台まで減少し、老年人口(65歳以上)が... -

医学教育モデル・コア・カリキュラム
医学⽣が卒業までに身につける必要のある実践的診療能⼒(知識・技能・態度)、それに対する学修⽬標を記した医学教育モデル・コア・カリキュラムというのがあります。... -

医師国家試験 合格発表
3月15日は医師国家試験の合格発表がありました。 合格者が92.4%で9547人が合格、4月から新しく研修医として働きます。 都農町で実習をした医学生からも合格報告の連絡... -

春はメンタル不調になりやすい
春は精神的に調子が悪くなりやすい時期と言われています。 日によって寒かったり暖かかったりで、気候の変化から体調が崩れやすい。 また卒業や入学、就職、人事異動な... -

三寒四温
冬から春にかけて、寒かったり暖かかったりという日が続きますね。 寒い日が三日ほど続くと、その後四日間くらいは暖かい日が続くというのを三寒四温といいますが、元は... -

一般用医薬品の3種類
一般用医薬品には第1~3類の3種類があります。 第1類:副作用・飲み合わせなどで安全性上、特に注意が必要 一部の解熱鎮痛剤や毛髪剤など 第2類:副作用・飲み合わせな... -

OTC医薬品
前回紹介した医薬品の3種類ですが、薬局やドラッグストアで購入可能な薬「要指導用医薬品」と「一般用医薬品」を合わせてOTC医薬品といいます。医療機関で処方してもら... -

医薬品の分類(医療用・要指導・一般用)
前回紹介したアライというのは、要指導医薬品というのに分類されて販売されます。 医療機関で医師が診察して処方箋を出し、薬局で調剤されて渡されるのが「医療用医薬品... -

アライ②
脂肪分解酵素リパーゼの働きを抑えて、脂肪吸収を減らすアライですが、「油の漏れ(34.2%)」「便を伴う放屁(23.3%)」などの消化器症状が副作用としてあります。食事... -

アライ①
内臓脂肪減少薬「アライ」というのが、薬剤師のいる薬局にて処方箋なしで来月から購入できるようになるというニュースが今週流れていました。 人の名前っぽいですが、「... -

猫飼いだしたらしいね
こんにちは、医療ソーシャルワーカーの田渕です。 前回、猫を飼い始めた事を書かさせて頂きました。 飼う事になった翌日に職場の猫派のみんなに報告すると、みなさん自...

 7
7